産業用ロボットを使うためのプログラムを作成する
産業用ロボットを使って作業を行うためには、産業用ロボットにプログラムを与えて、目的の動作が行えるように教え込む「ティーチング」といわれる作業が必要になります。
例えば、ロボットアームに対象物を運搬させたいときは、
- 対象物のある位置にロボットの先端を移動させる
- ロボットに対象物を持たせる
- 対象物を置きたい位置まで移動させる
- ロボットに対象物を置かせる
- ロボットの先端をもともとの位置(原点)へ移動させる
という動作をティーチングすることで、自動的に同じ作業をさせることができるようになります。
産業用ロボットのティーチングを行うことで、人でなければできなかった作業を、ロボットに行わせることができ、作業効率の向上や人件費削減が実現できます。
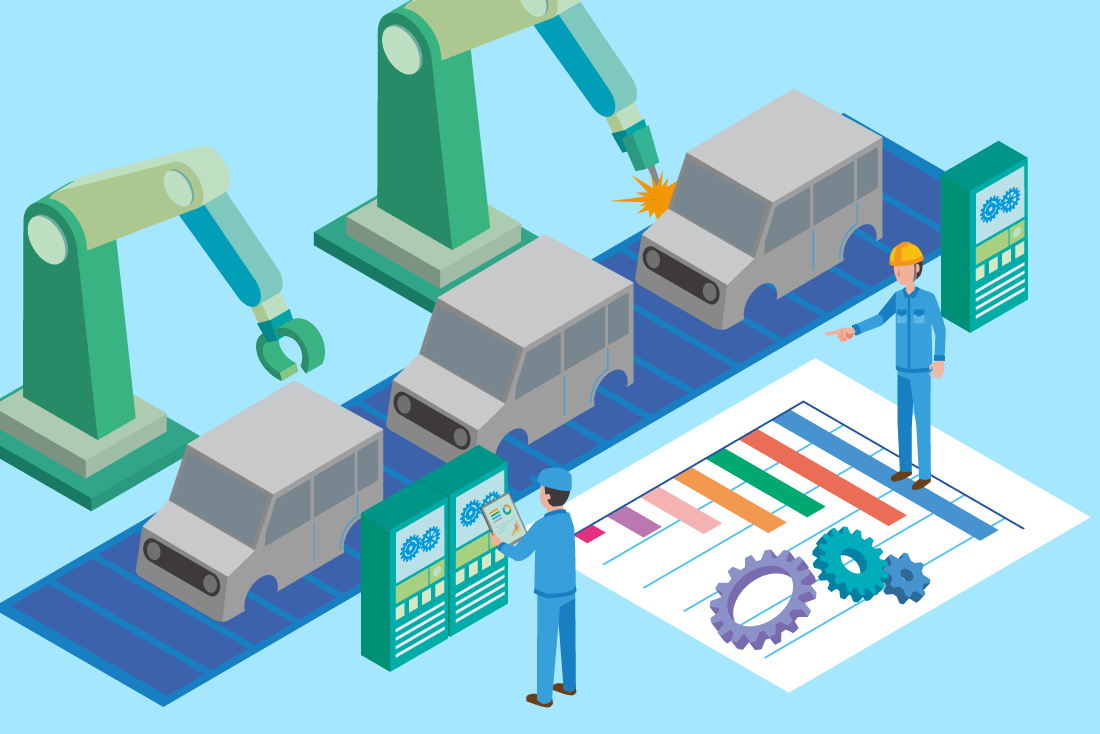
産業用ロボットを扱うには資格が必要
産業用ロボットは生産性や作業効率の向上に効果的な設備ですが、扱い方を間違えると大きな事故につながる恐れもあります。そのため、リスク軽減や安全性の確保のために、産業用ロボットを扱うには、法律によって資格の取得が義務付けられています。
産業用ロボットの操作に必須とされる資格は「産業用ロボットの教示等の業務に係る特別教育」と言い、労働安全衛生法が定める「特別教育」を受けることで取得できます。ロボットへの直接的な作業だけではなく、間接的におこなう作業員に対しても必須となります。
特別教育の内容は「教示」「検査」の2種
産業用ロボットに関わる作業員に求められる資格は、大きく分けて「教示」「検査」の2種類に分類されています。
(1)教示
「教示」は、ロボットへ動作を記憶させるティーチング作業をおこなう際、必須となる資格です。産業用ロボットに動作を記憶させ、適切な処理を行えるようにプログラミングを行います。また、安定した作業が継続するためのスピードの設定なども行います。ロボットの近くで行う作業のため危険も伴いますが、特別教育を受けることで、安全に作業を行うための知識や技術などを習得することができます。
(2)検査
「検査」の資格が求められるのは、産業用ロボットの修理・調整など、メンテナンスを行う業務です。機器を停止した状態で作業を行うことが多いですが、場合によっては停止せずに稼働範囲外で作業を行うこともあり、稼働中の機器を安全に検査するためにも特別教育を受け、資格を取得することが義務付けられています。
資格のいらない産業用ロボットは?
産業用ロボットを操作するには資格が必要ですが、使用するロボットの出力が80W未満であれば、特別教育を受講することなく操作することができます(2021年2月現在)。資格を求められる機器と比べて出力が低く、作業中に誤ってぶつかったとしても大きな事故に繋がる心配がありません。
